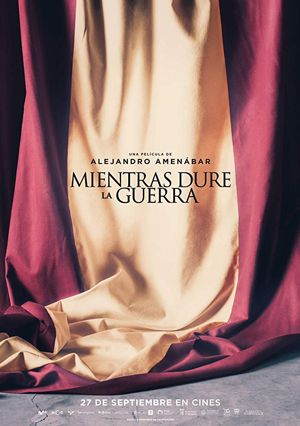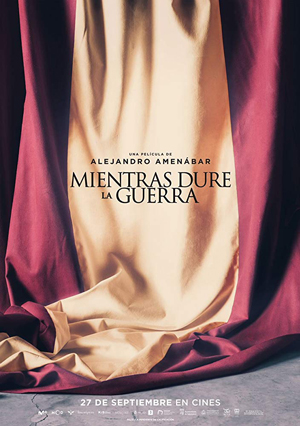 2004年の「海を飛ぶ夢」でアカデミー外国語映画賞を受賞したアレハンドロ・アメナーバル(Alejandro Amenábar)の最新作です。15年前の作品が代表作というとかなり高齢かと思われるかも知れませんが、まだ40代の監督です。
2004年の「海を飛ぶ夢」でアカデミー外国語映画賞を受賞したアレハンドロ・アメナーバル(Alejandro Amenábar)の最新作です。15年前の作品が代表作というとかなり高齢かと思われるかも知れませんが、まだ40代の監督です。
映画は1930年代にサラマンカ大学の終身学長だった哲学者で詩人のミゲル・デ・ウナムーノ(Miguel de Unamuno)の晩年を描く物語。フランシスコ・フランコ(Francisco Franco)たちの反乱軍によってスペイン内戦が始まり、共和国政府と反乱軍の両勢力の間で苦悩する哲学者の姿が描かれます。
同時に、フランコが反乱軍内部のパワーバランスで総統(caudillo)の地位に就き、一介の軍司令官が独裁者へと変貌していく様子も描かれます。時代の波に流されていく対極的な二人を並べながらも善悪を評価することなく、またどちらかを断罪するわけでもなく、淡々と歴史の趨勢を見せていくあたりがこの作品の特徴と言えるでしょう。

映画の始まりは画面いっぱいに映し出されるスペイン共和国旗。この三色旗(la tricolor)で第二共和政の時代だということを示すわけですが、この後も旗の掛け替えで政権交代を伝え、エンディングもまた画面いっぱいの旗で締めくくることになります。ちなみに伝統的な赤と黄の他に共和国旗で使われている紫(morado)はカスティーリャ・イ・レオンを象徴する色だそうです。

よく知られているようにサラマンカ大学はスペイン最古の大学で、その歴史は12世紀頃まで遡るといわれる知の殿堂です。若くしてその終身学長の座を射止めたウナムーノは時代を代表する知識人であり、映画で触れられるようにノーベル賞候補の噂もあったようですが、良くも悪くも多分に政治的な人物で、それによって毀誉褒貶に晒されることになります。

共和国政府寄りの立場で権威を高めたウナムーノが、その言動から反乱軍支持と受け止められて任を解かれ、後の反乱軍優勢で学長の地位に返り咲いたものの、1936年10月12日の“民族の日”(Día de la Raza)の演説で再び職を解かれます。映画の中で何度も語られる“言いたいことを言う”という本来の姿がエンディングの演説シーンで具現化するわけですが、逆にいえばそれまでは世渡りのために沈黙していたとも言えます。

もっとイジワルな見方をすれば、彼の要求を聞き入れなかったフランコに対し、病を患い、老い先みじかいことを悟った彼が精一杯の仕返しをしたとも考えられるでしょう。こういった映画ではウナムーノが語るような社会正義を安易に崇めがちですが、この場面をクライマックスに置きながらも客観的な視点で描ききったアメナーバル監督に好感が持てます。

フランコの扱いも同様で、凡庸で頼りげない司令官が、関係者の思惑が絡み合ってリーダーに選ばれ、凡庸であるが故に着実な選択をしていくあたりを冷静に描いていきます。描かれている時代のせいかも知れませんが、極悪非道な印象はまったくありません。この映画で悪役っぽい風情を漂わせているのは、外人部隊を率いてフランコと共に闘ったホセ・ ミリャン・アストライ(José Millán-Astray)ぐらいでしょうか。

この隻眼隻腕の将軍アストライを演じたのは「スモーク・アンド・ミラーズ」「誰もがそれを知っている」などでお馴染みの人気俳優エドゥアルド・フェルナンデス(Eduard Fernández)。フランコを演じたのは「星の旅人たち」に出ていたというサンティ・プレゴ(Santi Prego)。
そして主人公ウナムーノを演じたカラ・エレハルデ(Karra Elejalde)は「雨さえも」でコロンブスを演じていた人。その他、フランコの兄弟ニコラス役で「マジカル・ガール」のお父さんルイス・ベルメホ(Luis Bermejo)、サラマンカ市長夫人アナ・カラスコ役で「ジュリエッタ」に出ていたナタリー・ポサ(Nathalie Poza)がキャスティングされています。

[仕入れ担当]