 家父長的で閉鎖的な宗教コミュニティで連続レイプ事件が起こり、それにどう対応すべきか、女性たちが話し合うという物語です。
家父長的で閉鎖的な宗教コミュニティで連続レイプ事件が起こり、それにどう対応すべきか、女性たちが話し合うという物語です。
原作はカナダ人作家ミリアム・トウズ(Miriam Toews)が、2005年から2009年にかけてボリビアの人里離れたメノナイトのコミュニティ、マニトバ(Manitoba Colony)で起こった事件にインスパイアされて書いた2018年の同名小説。実際の事件は犯人たちが逮捕されて終わるわけですが、ミリアム・トウズは被害の当事者である女性たちがどう反応し、どう行動するか、その部分にフォーカスしてこの会話劇を創作しています。つまり完全なフィクションです。

論点はコミュニティを維持するか否かで、選択肢としては男性たちを赦してこのままの生活を続ける、男性たちと闘ってコミュニティの改革を図る、ここから立ち去るの3つがあります。難しいのは彼らがメノナイトの集団であり、強い信仰心で結びつき、宗教に基づく生活を旨としていること。赦しはキリスト教の根源であり、メノナイトの平和主義は闘争を忌避します。地域の指導者(男性)は、赦すことで天国に行けると説きますので、それ以外の選択肢は信仰に背くことだと捉える女性もいるわけです。

特殊な世界での出来事のようですが、実は現代社会の多くの局面で、偏向した社会規範によって女性の意思や行動が制約を受けているわけです。「アウェイ・フロム・ハー」「テイク・ディス・ワルツ」「物語る私たち」のサラ・ポーリー(Sarah Polley)が脚本化し、出産直後にもかかわらず監督まで務めた思い入れが理解できます。その甲斐あって彼女はこの作品で2023年アカデミー賞の脚色賞を受賞しました。製作は「ファーゴ」「スリー・ビルボード」「ノマドランド」のフランシス・マクドーマンド(Frances McDormand)で、原作にはない人物の役で少しだけ出演しています。
映画の始まりは一人の女性がベッドで目覚める場面。内ももの打撲や擦り傷が映り、就寝中にレイプされたことが示されます。コミュニティ内の一部の男たちが、ナス科の植物ベラドンナを原料とする家畜用鎮静剤を窓から噴霧し、昏睡状態に陥った女性を暴行していたのです。ほどなく犯人たちが逮捕され、家畜を売って彼らの保釈金を支払うため、男たちが街に出払います。

集落に残った女性たちが納屋に集まり、今後どうするか議論を始めます。猶予は男たちが街から帰ってくるまでの2日間。まず選択肢を描いた図が示されます。農地が広がる図=このまま何もしない、刃物をもって対峙する図=男たちと闘う、あちらを向いた馬の図=去るの3つです。
なぜ図なのかというと、彼女たちの母語であるメノナイト低地ドイツ語(Plautdietsch)は文字を持たないから。
議論を記録するためにオーガストを呼び入れます。子どもの頃に親と共にこの集落から追放され、英国で教育を受けた後にデモに参加して国外退去処分になり、集落に戻ってきて教師をしている男性です。

映画では全員が英語で話しますので彼の位置づけがわかりにくくなりますが、原作は、全員がノナイト低地ドイツ語で話し合ったことをオーガストが英語で記録したものということになっています。つまり小説の語り手はオーガスト。それに対して映画では、大人たちの論争を見守る10代の少女オーチャが語り手になり、それがサラ・ポーリーの映画らしさを高めています。

映画の主な登場人物たちは3つの家族で、フランシス・マクドーマンド演じるスカーフェイスは何もしない派。ほどなく話し合いの場から立ち去り、小説と同じく、残った2家族が議論することになります。

一つはジュディス・アイビ(Judith Ivey)演じるアガタの一家で、ルーニー・マーラー(Rooney Mara)演じる長女オーナも、クレア・フォイ(Claire Foy)演じる次女サロメも闘う派。
もう一つはシーラ・マッカーシー(Sheila McCarthy)演じるグレタの一家で、ジェシー・バックリー(Jessie Buckley)演じる長女マリチェは赦すべきだと主張し、その妹であるミシェル・マクラウド(Michelle McLeod)演じる次女メジャルは闘う派です。

そのうち、オーナはレイプによって妊娠していること、サロメの幼い娘はレイプで負傷し今も抗生剤を与える必要があること、外で子どもたちの世話をしているオーガスト・ウィンター(August Winter)演じるメルヴィンは、レイプのショックで子どもとしか話せなくなったことなどがわかってきます。

議論が収束せず散会になった後、モンキーズのDaydream Believerを大音量で響かせながら車が集落に入ってきます。この脳天気な音楽を流しているのは2010年の国勢調査団で、要するに外部の人間なのですが、彼らからマリチェの夫クラースが不足分の保釈金を確保するため集落に戻って来ると伝えられ、女性たちは話し合いを再開します。

オーナとメジャルは立ち去る派に転向しますが、サロメは依然として闘う派で、娘を危険な目に遭わせた男たちを殺したいと告白します。しかし母アガタから信仰の原則を説かれ、立ち去る派に転向します。マリチェだけが赦す派ですが、彼女が夫クラースから虐待を受け、それを母グレタが容認していたことが明らかになるなど、それぞれの事情が表面化して議論が白熱します。
激しい論戦の結果、立ち去ることに決まり、子どもたち、特に10代の男の子をどうするかなどに論点が移っていきます。小説ではここで集落の男の子が絡んで若干スリリングな展開があるのですが、序盤で登場する地域の指導者と同じくそれは割愛され、映画にはベン・ウィショー(Ben Whishaw)演じるオーガストしか男性は出てきません。実は終盤の拳銃は指導者の持ち物なのですが、彼の存在に触れませんので唐突に現れることになります。
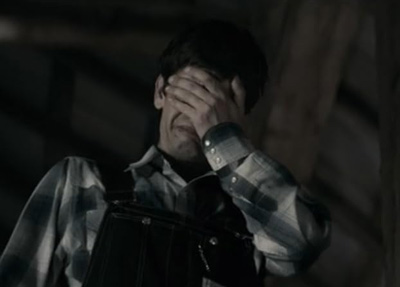
隔絶されたコミュニティであることをイメージさせる、まっすぐ続く一本道が印象的な集落を映像に収めたのは「アウェイ・フロム・ハー」「テイク・ディス・ワルツ」のリュック・モンテペリエ(Luc Montpellier)。色褪せた感じの映像が物語の雰囲気にしっくり馴染みます。ロケ地はカナダだそうですが、南十字星に言及して舞台が南半球であることをさりげなく示唆します。

ミリアム・トウズはカナダのマニトバ州にあるメノナイト・コミュニティの出身だそうで、メキシコのメノナイトを題材にした小説を発表するなど、この独特な生活習慣を持つ宗教集団を好んで取り上げている作家です。ですから原作小説では、スカートの裾と靴下の隙間から肌が見えてはいけないとか、スカーフで髪を覆うといった服装の厳格さなども詳しく記していますが、映画ではそういったこだわりは排除したようです。

重要なのはメノナイトの宗教観や風習といった特殊性ではなく、“赦し(forgiveness)は許可(permission)と混同されやすい”という、どこの世界でも通用する普遍的な指摘でしょう。そういう点で、多くの女性が観るべき映画だと思います。
公式サイト
ウーマン・トーキング 私たちの選択(Women Talking)
[仕入れ担当]



