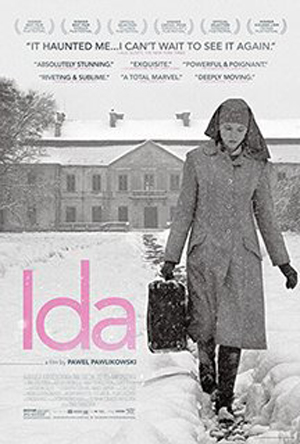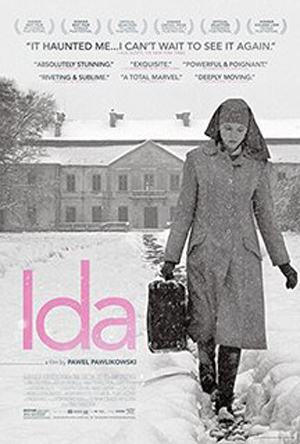 むかし風のスタンダードサイズで撮られたモノクロのポーランド映画です。画像の縦横比を活かし、上部に余白をとった構図がとてもスタイリッシュ。映画作りを研究している方には、何かしら得るものがありそうです。
むかし風のスタンダードサイズで撮られたモノクロのポーランド映画です。画像の縦横比を活かし、上部に余白をとった構図がとてもスタイリッシュ。映画作りを研究している方には、何かしら得るものがありそうです。
物語は、孤児として修道院で育てられた少女が18歳になり、修道女となる誓願式の前に、唯一の肉親である伯母に会いに行って、両親(伯母にとっては妹夫婦)の最期を知ろうと2人で旅に出るというもの。
信仰に篤く、世間知らずの少女と、世俗にまみれた伯母が一緒に過ごすことで、それぞれが自らの殻を打ち破っていくお話です。
表面的にはそれだけのストーリーですが、本作の舞台が1962年のポーランドということで、話がややこしくなります。つまり、少女の両親が亡くなった1940年代半ばのポーランドを振り返るということが、重たいテーマに繋がっていく仕掛けなのです。
1940年代といえば第二次世界大戦中であり、ドイツとソビエトに挟まれたポーランドは、さまざまな苦難を味わった時期。かたや1962年のポーランドは、スターリン批判後の社会主義国であり、民主化運動の萌芽が微かに見え始めていた時期。
映画の冒頭、修道院でアンナと呼ばれていた少女が、傷んだキリスト像を仲間と修復し、庭に置き直します。社会主義下で行われていた宗教弾圧を想像させるシーンです。その後、修道女の部屋に呼ばれたアンナは、彼女の引き取りを拒否した伯母がいることを知らされ、誓願式の前に会いに行くように言われます。
伯母のヴァンダは、裁判所の判事という公職にありながら、酒や男で自堕落な生活を送っている女性。彼女はアンナに会うなり、あなたの本名はイーダで、自分たち家族はユダヤ系だと告げます。敬虔なキリスト教徒として暮らしてきたアンナには青天の霹靂です。
そうなると、両親の末期はポグロムに他ありません。当時、ユダヤ人は共産主義者との繋がりを疑われてカソリック教会から迫害されたり、ナチスドイツの主張に乗じた隣人たちから略奪されたりしていたことは「ソハの地下水道」で描かれていた通りです。
ですから、両親の墓所を参りたいというアンナ改めイーダに対し、ヴァンダは「神が存在しないと知ることになっても良いのか」と確かめるのです。
また、大戦中、ドイツとソ連に占領されていたポーランドではレジスタンス運動が行われており、ユダヤ人を救済していたジェゴタのような地下組織もあれば、「あの日 あの時 愛の記憶」で描かれたような民族的な運動もあり、そのあたりはとても複雑です。
伯母のヴァンダもレジスタンスに参画していたようですが、神を否定し、戦後、要職に就いていることから共産主義者に連なっていた可能性が高いわけで、死刑を判決したこともあるとイーダに語るくだりには、体制を守るために処刑するのはポグロムと同じだという悔恨が滲んでいるような気がします。
キリスト教徒とユダヤ教徒、親ソビエト派と親ドイツ派と民族主義者、そして共産主義のような政治思想や貧困の問題。さまざまな背景と利害をもった人々が複雑に絡み合っていた時代のポーランドですから、きっと日本人には見えていない部分が多々あります。だからといってユダヤ問題だけに単純化して観る映画でもありません。
ついでながら、モーツァルトの“ジュピター”やコルトレーンの“ナイマ”といった選曲もとてもお洒落で、スタイリッシュな映像に合っています。不便な映画館で、お勧めしにくいところですが、欧州近代史に関心をお持ちの映画好きなら観ておいても損はないと思います。
毎年8月には、戦争や暴力について考えさせられる映画を観て(去年はこの映画)、改めて平和のありがたさを噛みしめています。東欧や中東は相変わらずで、ニュースを観る度にうんざりしますが、せめて自分たちが世界をうんざりさせることがないように強い心を持ちたいものです。
公式サイト
イーダ
[仕入れ担当]