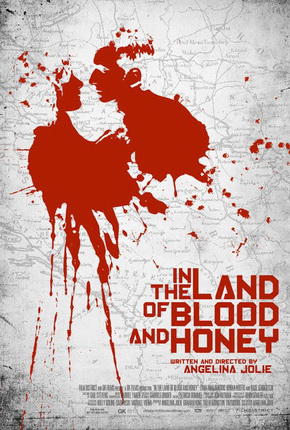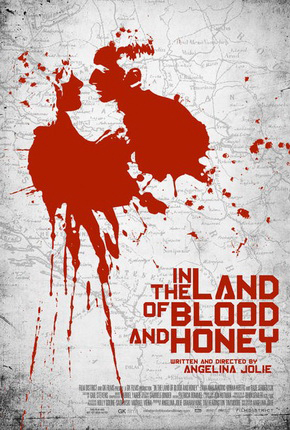 注目を集め続けるハリウッド女優、アンジェリーナ・ジョリー(Angelina Jolie)の初監督作品です。米国では2011年末に公開されているのですが、日本では遅れること1年半、ようやくこの夏に公開となりました。
注目を集め続けるハリウッド女優、アンジェリーナ・ジョリー(Angelina Jolie)の初監督作品です。米国では2011年末に公開されているのですが、日本では遅れること1年半、ようやくこの夏に公開となりました。
テーマは1992年から1995年まで続いたボスニア・ヘルツェゴヴィナの内戦。UNHCRの親善大使を務めるアンジェリーナ・ジョリーらしい視点に溢れた作品です。とはいえ、都心部の上映館は新宿の1館のみ。パートナーのブラッド・ピット(Brad Pitt)が製作・主演したゾンビ映画「ワールド・ウォーZ」が同じ館で上映されていましたが、あらゆる意味で対称的な映画です。
幕開けは、ムスリム人(Bošnjaci)女性の絵描きアイラと、セルビア人の警官ダニエルがデートで訪れたボスニア・ヘルツェゴヴィナのディスコ。バンドの演奏がスローな曲に変わり、身体を寄せて踊り始めた瞬間、店内で爆破が起こります。4年近く続く内戦の始まりです。
この内戦は、社会主義だったユーゴスラビア連邦が崩壊していく中で、ボスニア・ヘルツェゴヴィナの独立を推進したムスリム人と、それに不満を抱いたセルビア人の対立によるもの。ムスリム人が多数派でしたが、歴史的にユーゴスラビアの中心であり、旧ユーゴ時代の軍部を掌握していた隣国セルビア共和国がセルビア人勢力を支援したため、ムスリム人が苦境に立たされました。
場面は変わって、アイラが姉と姉の子どもと暮らす集合住宅。武装したセルビア人たちがやってきて、ムスリム人の男性たちを処刑し、若い女性たちを身の回りの世話をさせるために宿舎に連れ去ります。そこは女性たちの人格が完全に無視され、日常的に性的暴力が繰り広げられる世界。
セルビア人側の将軍の息子であるダニエルは下士官として従軍しており、たまたま彼が宿舎にいたことから、連行されてきたアイラに気づいて救い出します。
自分の所有物(property)だから手を出すなと兵士に言っておいたので安心していい、とダニエルは言うのですが、助かったと安堵しつつも、所有物という言葉に複雑な表情を浮かべるアイラ。
その後、ダニエルが異動になり、アイラは兵舎から脱走して姉と合流しますが、戦況の変化と共に状況も変わります。抵抗を続けるムスリム人たちは、仲間のタリックがわざと捉えられて自白することで、アイラが再びセルビア人側の宿舎に連行されるように仕組みます。
アイラが密命を帯びていることを知らず、お抱えの絵描きという立場を与えて彼女を守ろうとするダニエル。しかし、父親である将軍は、自分の親たちを殺したムスリム人たちに報復すべきだという考え方であり、アイラの存在を容認するはずはありません。ダニエルとアイラにはさまざまな苦難が待ち受けています。
“血と蜜の大地へ”という原題の通り、ところどころ恋愛映画のような情景が織り込まれますが、その背後には常に血なまぐさい戦闘が控えているわけで、甘いシーンに漂う不穏な空気感、緊迫感がリアルな映画です。
恐ろしいのは、相手を屈服させるための武器として、性的暴力が振るわれること。確か、民族浄化(ethnic cleansing)という言葉は、この内戦から使われ始めたものだと思いますが、組織的な性的暴力もこの主要な手段です。現在も中東やアフリカの紛争地域で深刻化していて、今年4月のG8外相会合では中心議題のひとつとして取り上げられていました(閣僚宣言)。
また、戦争には必ず、対立を煽ることで自らのプレゼンスを発揮する個人や集団が存在するわけですが、弱い立場の女性が、敵に対する恐怖心から彼らに煽られ、また義憤や怨恨から彼らに共感し、結果的に紛争を支えてしまうことも恐ろしいとことだと思います。
映画で描かれた内戦がデイトン合意でとりあえずの終結を迎えるのは1995年。日本では、バブル経済崩壊後とはいえ、六本木のヴェルファーレが流行っていたり、浮ついた空気が漂っていた頃ですから、その差には愕然とするものがあります。
昨年の8月は「あの日 あの時 愛の記憶」、一昨年の8月は「未来を生きる君たちへ」を観て、戦争や暴力について考えましたが、今年の8月15日はこの映画を反芻しながら迎えました。
68回目の終戦記念日ということは、68年間戦争していないということであり、それを幸福なことだと思うとともに、右とか左とか関係なく、対立を煽る連中には用心しなくてはいけないと改めて思いました。
公式サイト
最愛の大地(In the Land of Blood and Honey)facebook
[仕入れ担当]