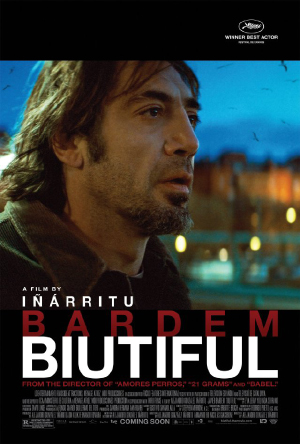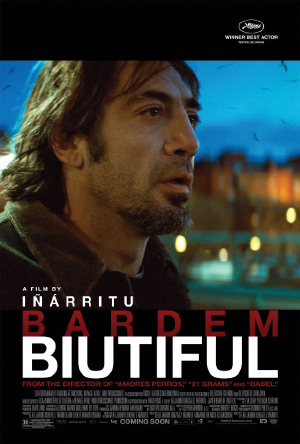監督は「アモーレス・ペロス」や「21グラム」のアレハンドロ=ゴンサレス・イニャリトゥ(Alejandro González Iñárritu)。撮影はイニャリトゥ作品の他、「ブロークバック・マウンテン」や「抱擁のかけら」で知られるロドリゴ・プリエト(Rodrigo Prieto)。この組み合わせを見ただけで上質の映像が約束されたようなものですが、カンヌの主演男優賞を獲ったハビエル・バルデム(Javier Bardem)が、それに値する素晴らしい演技で物語を支えます。
映画の舞台はバルセロナ。といっても、以前ハビエル・バルデムが主演した「それでも恋するバルセロナ」のような陽光あふれるバルセロナではなく、空気が淀んだようなバルセロナです。中盤で映るサグラダ・ファミリア(La Sagrada Família)やアグバル・タワー(Torre Agbar)の位置関係を見ると、街の中心からそれほど遠くないエリアだと思うのですが、こういう場所もあるんだなぁという感じでした。
ハビエル・バルデム演じるウスバルは、中華系やセネガル系の不法移民に仕事を斡旋したり、際どい仕事をしながら2人の子どもと暮らしていますが、血尿が出て病院で検査すると前立腺ガンで余命2ヶ月の宣告。残りの人生を良い人間として生きようと考え始めます。
ときどき子どもに会いに来る、別れた妻は心の病を抱えた薬物依存症。偽ブランドや海賊版CDを作っていた中華系移民を工事現場に送り込んだら使えないというクレーム。その上、街頭で物売りをしていたセネガル系移民が警察の取り締まりにあい、ウスバルも拘留されるなど、さまざまな面で追いつめられていきます。そのぎりぎりの人生を送るウスバルの家族愛を軸に、不法移民の家族の肖像が語られていきます。
映画の冒頭、ウスバルが娘のアナに父の形見のダイヤモンドの指輪の話をします。そしてシーンが変わり、雪の中に立つウスバルとやや若い男。会話した後、歩き始める男を、"Qué hay?"(何があるの?)と無邪気に後を追うウスバル。この若い男が誰かは、後で分かるのですが、これを見ただけで期待が高まる素晴らしいシーンです。そして、この重いテーマの映画を後で反芻するとき、救いとなるシーンでもあります。
娘のアナを演じたHanaa Bouchaib、息子のマテオを演じたGuillermo Estrellaが2人ともとても可愛らしく、また妻のマランブラを演じたMaricel Álvarezも映画初出演ながら、リアリティのある素晴らしい演技でした。
移民という現代ヨーロッパを象徴するテーマと、家族の絆という普遍的なテーマを、メキシコ人監督らしい霊的な要素を交えながら描いた美しい映画です。一見の価値はあると思います。
[仕入れ担当]