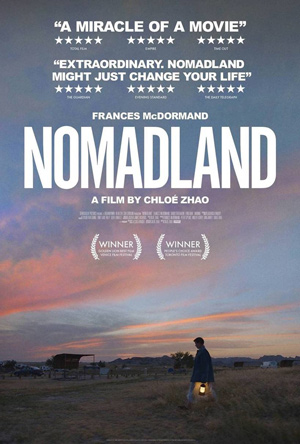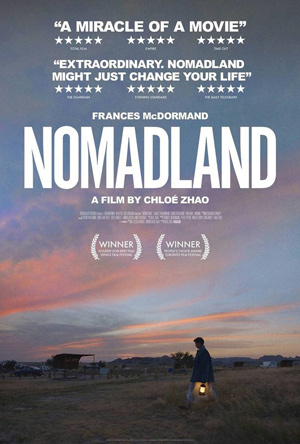 先週の「ミナリ」と並んで今年度アカデミー賞の有力候補に挙げられている映画です。どちらもアジア系の監督でありながら、米国の伝統的価値観である開拓者精神のようなものを取り込んでいるところが興味深いところですが、映画の完成度としては本作に軍配が上がりそうな気がします。とても質の高い作品です。
先週の「ミナリ」と並んで今年度アカデミー賞の有力候補に挙げられている映画です。どちらもアジア系の監督でありながら、米国の伝統的価値観である開拓者精神のようなものを取り込んでいるところが興味深いところですが、映画の完成度としては本作に軍配が上がりそうな気がします。とても質の高い作品です。
2017年に出版されたジェシカ・ブルーダー(Jessica Bruder)のノンフィクション「Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century」を下敷きにした映画で、この本に感銘を受けた女優のフランシス・マクドーマンド(Frances McDormand)が映画化権を買い取り、デビュー作がサンダンス映画祭やカンヌ映画祭で高い評価を受けた新人監督のクロエ・ジャオ(赵婷:Chloé Zhao)を起用して製作したもの。ほぼすべての場面にフランシス・マクドーマンド演じる主人公のファーンが登場する、まさに彼女の映画になっています。

舞台となる米国中西部の砂漠や荒野をアンドリュー・ワイエスを思わせる詩的な映像で撮ったのは、監督の公私にわたるパートナーであるジョシュア・ジェームズ・リチャーズ(Joshua James Richards)。表情やたたずまいでさまざまなことを伝えるフランシス・マクドーマンドの演技を、夜明けや夕暮れ時の光を使って巧みにとらえています。それにしても彼女の演技力はスゴイですね。「ファーゴ」「スリー・ビルボード」に続いて3度目の主演女優賞を獲るのではないでしょうか。

物語は長く住んでいた規格型住宅(tract house)を離れ、フォード・エコノラインのバンを改造して先駆者(Vanguard)と名付けたキャンピングカーで暮らすようになったファーンが、同じように移動しながら生活する人々=ノマドと触れ合うことで、それまで信じていた常識や、とらわれていた過去を見つめ直していくというもの。彼女に惹かれる初老の男性デイブを演じたデヴィッド・ストラザーン(David Strathairn)を除いて、主だった登場人物のほとんどが実際に車上生活を送っている高齢のノマドたちです。

その中で唯一の異質な登場人物が、「イントゥ・ザ・ワイルド」のクリスを思わせるデレクというバックパッカー。彼と再会したファーンがシェイクスピアのソネット18を諳んじてみせるのですが、原作にもなく、この世界とはまったく無関係な若くて車もなく働いていない人物を敢えて登場させ、”君の永遠の夏は色あせない”という詩を聞かせたあたりに、ジェシカ・ブルーダーの社会批判から少し距離をおいた、この映画のテーマがあるように思いました。

原作とされているノンフィクションは、定住することをやめ、家財道具を積み込んだキャンピングカーで各地を移動しながら季節労働で生計を立てている高齢者たちの実態を記録したもので、映画にも実名で登場するリンダ・メイを中心に彼女にかかわる人々の暮らしぶりが描かれます。仕事を失った人々が新天地を求めて放浪するという点でいえば現代版「怒りの葡萄」といったところですが、昔と大きく違うのが彼らの重要な働き口にアマゾン物流センターが含まれること、彼らに定住の意志がなく永遠の放浪を望んでいること、そしてそのほとんどが高齢者であるということです。

彼らのようにキャンプサイト(RV park)で寝泊まりしながら働く人々をワーキャンパーと呼ぶそうですが、高齢者が多い理由としてジェシカ・ブルーダーは家賃の高騰と公的年金の少なさ(リンダは月550ドルほど)を挙げています。また2010年頃にワーキャンパーが急増したのは、金融危機で確定拠出型年金が元本割れしたことやサブプライム絡みで持ち家を手放した人が多かったことも関係しているようです。いわば制度の谷間に落ちて行き場を失った人たちです。

それでも本人たちはこういった生活に楽しみを見出しているようで、たいていペットを飼っていますし、各地でGTG(Get Togather)と呼ばれる集会を行っています。その最大のものが映画に実名で登場するボブ・ウェルズが主宰するラバー・トランプ・ランデブー(RTR:タイヤのrubberと流れ者のtramp)で、2017年には500台以上のバンがアリゾナ州の砂漠クォーツサイト(Quartzsite)に集結したそうです。ヒッピー世代の彼らにとっておそらく一種のビーイン(Human Be-In)なのでしょう。ヒッピームーブメント最盛期の1967年夏をサマー・オブ・ラブと呼ぶことと上記のシェイクスピアの引用意図も繋がっていそうです。

ノマドたちの聖典が中年期のジョン・スタインベックが愛犬とキャンピングカーで旅した旅行記「チャーリーとの旅」というあたりにも彼らの心の在処が現れています。ちなみにその他の必読書としてはウィリアム・リースト・ヒート・ムーン「ブルー・ハイウェイ―内なるアメリカへの旅」、エドワード・アビー「砂の楽園」、ジョン・クラカワー「荒野へ」、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー「森の生活」、シェリル・ストレイド「わたしに会うまでの1600キロ」が挙げられていて、旅に対する考え方がうかがわれます。

映画では社会問題よりもワーキャンパーたちの意識にフォーカスし、彼らが自由を求め、敢えて苦難を受け入れている姿勢に重心を置きます。たとえば彼らをキャンパーフォース(CamperForce)と呼んで繁忙期の人員補充をしているアマゾンに関して、原作では筋肉痛でも働けるように倉庫の壁にジェネリックの鎮痛剤が備えられている非人間的な環境や、本当の狙いが低所得者を雇うことで適用される税額控除であることを糾弾しているのに対し、映画では似たような労働者の出会いの場としてあっさりと描かれます。
このアマゾンのシーンで重要なのは雇用形態の問題よりも昼食時に同僚のアンジェラが見せるタトゥです。スミスの「Rubber Ring」から引用したタトゥを見せ、続いてモリッシーの「Home Is A Question Mark」の一節を示します。腕に彫られた”Home, is it just a word? Or is it something that you carry within you?”は、その生き方をホームレスではなくハウスレスだという彼らの主張に通じるものです。
このような視点は、映画のために創造されたファーンの生き方でも明確に打ち出されており、物語の軸となるのは彼女が長く暮らしたエンパイアの町や夫の思い出というくびきから解き放たれ、何にも縛られない人生を掴んでいくまでの心の旅です。もちろん彼女の人物像は、演者であると同時に製作者でもあるフランシス・マクドーマンドの思いが強く反映されているはずで、一つ一つの小さなエピソードに自由であるということに対する作り手の考え方が滲みます。

ファーンが住んでいたとされるUSジプサムの企業城下町エンパイアは、原作では大企業に依存してきた人々が、住宅市場の低迷で石膏ボードが売れなくなり、2010年12月2日で一瞬にして仕事も社宅(2日分の賃金で1ヶ月分の家賃を賄えるそう)も失ったというエピソードに続いて、同じ頃、その100キロ南に位置するファンリー(Fernley)のトレーラーパークには不安定な臨時雇いで働くプレカリアートたちが集まっていたという流れで紹介されます。そして時給11.5ドルでクリスマスセールの出荷作業を行うアマゾンのキャンパーフォースの説明へと進み、キャンプ場や森林の管理、狩猟場の動物処理などワーキャンパーたちが従事するさまざまな職種が記されます。

映画でもいくつかの仕事が描かれますが、注目すべきは原作に登場しないのにアマゾンと並んで象徴的に取り上げられる場所、サウスダコタのウォール・ドラッグ(Wall Drug)とバッドランズ(Badlands)国立公園でしょう。化石で有名なこの公園内をさまよったファーンは、デイブから何か見つけたかいと訊かれて”rocks”と答えます。このセリフに限らず、さまざまな仕掛けが施されたこの作品、じっくり浸れる映画館でご覧になるのがお勧めです。アカデミー賞の作品賞、監督賞、主演女優賞、撮影賞と併せて、脚色賞や編集賞にもノミネートされている理由がわかります。
[仕入れ担当]