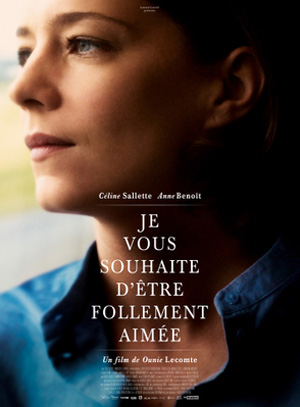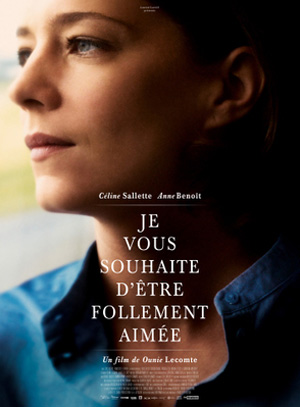 久しぶりに岩波ホールで観ました。監督は「冬の小鳥」のウニー・ルコント(Ounie Lecomte)。韓国生まれながら、牧師の養女としてフランスで育ち、女優を経て映画監督になった女性です。
久しぶりに岩波ホールで観ました。監督は「冬の小鳥」のウニー・ルコント(Ounie Lecomte)。韓国生まれながら、牧師の養女としてフランスで育ち、女優を経て映画監督になった女性です。
長編2作目となる本作もテーマは養子縁組ですが、前作とは異なり韓国には絡めていません。主人公エリザを演じたセリーヌ・サレット(Céline Sallette)も、その生母アネットを演じたアンヌ・ブノワ(Anne Benoît)もよくいるタイプの白人女性ですので、自らの伝記的要素を抑え、より普遍化させた作品といえるかも知れません。
主人公は理学療法士として働く既婚女性。小学生の息子が一人います。何がきっかけになったかは描かれませんが、ここ最近、実母を捜そうと手を尽くしているようです。しかし、実母の側の同意なく情報が開示されることはありません。自身の出自について知っているのは、フランス北部ベルギー国境の街、ダンケルクの孤児院で育ったということのみということで、パリの自宅に夫を残し、息子を連れてダンケルクに転居してきます。
小学校に転入した息子のノエ。カフェテリアの列に並んでいると、給食の補助員がソーセージを食べさせても大丈夫か確認します。いわれてみれば、ちょっと顔つきがエキゾチックです。演じたエリエス・アギス (Elyes Aguis)は、アスガル・ファルハーディー監督「ある過去の行方」でイラン人の連れ子の役だった少年ですので、わざわざそういう子役を選んだわけで、イスラム教徒だと勘違いされることに何らかの意味があるとわかります。
ところがノエの父親、つまりエリザの夫アレックスは、シャンパーニュ地方出身の男性という設定。演じているのもルイ=ド・ドゥ・ランクザン(Louis-Do de Lencquesaing)ですので、ペルシャ系でもアラブ系でもありません。日本人にはちょっとわかりにくい部分ですが、それを不思議に思う気持ちが終盤に伏線として機能します。
エリザはダンケルクでも理学療法士の仕事に就きます。さまざまな患者の体を屈伸させたり、マッサージしたりという毎日です。そんな患者の一人に、ノエの学校で補助員として働くアネットがいます。腰を痛めた際、ノエの母親がいることを知って治療を受けに来た彼女は、若いころに骨肉腫をわずらい、その後遺症にも苦しんでいます。
共通の話題ですから、当然のようにノエの話をします。しかしエリザはあまり私的な部分に踏み込んで欲しくないと思っているようです。それでも、若干、おせっかい気味に学校での話題を振るアネット。なぜかノエが気になって仕方ないという展開ですが、観客の誰もが気付くように、彼女こそがエリザの実の母親、ノエの祖母なのです。そしてノエにはエリザの父親の面影が宿っているのです。
後半で母娘であることが明らかになりますが、エリザはその事実を受け入れられません。なぜ受け入れられないか。そのあたりが親権放棄や養子縁組の難しさや、この監督なりのアンビバレンツな感情の描き方なのかも知れませんが、理由はずっと曖昧なままです。おそらく彼女の心の瑕ということなのでしょう。
アネットは未婚で出産し、子どもを孤児院に渡さざるを得ませんでしたが、子どもの父親に対する憎しみはありません。それどころかいまだ彼を擁護する気持ちを漂わせます。エリザはエリザで、善い人だから大切にするようにと養親から言われている夫をパリに残し、息子とダンケルクに転居してしまいます。フランスでは違法な手術をベルギーに行って受けるなど、さまざまな場面で夫を否定しているかに見えますが、いずれも合理的な説明はなく、この母娘の精神的な脆さを暗示するのみ。それが受け継がれ、それゆえに幸福を享受できないという運命論すら感じさせます。
フランス映画らしい内省的な女性映画です。解釈の余白を楽しむタイプの作品ですので、鑑賞後、どなたかと話し合いたくなると思います。
公式サイト
めぐりあう日(Je vous souhaite d’être follement aimée)
[仕入れ担当]