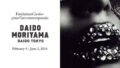サブプライムローン問題による金融危機を先読みし、逆張りしたウォール街の変わり者たち(outsiders and weirdos)にフォーカスした作品です。原作となったのは、投資銀行の裏話を描いた「ライアーズ・ポーカー」で1989年にデビューしたマイケル・ルイス(Michael Lewis)が、2010年に発表した同名のノンフィクション。関係者へのインタビュー中心の構成で、これが映画になるのか?という著作ですが、さすがサタデー・ナイト・ライブ出身のアダム・マッケイ(Adam McKay)監督、起こったことのばかばかしさを逆手にとって、しっかり笑える映画に仕上げています。
サブプライムローン問題による金融危機を先読みし、逆張りしたウォール街の変わり者たち(outsiders and weirdos)にフォーカスした作品です。原作となったのは、投資銀行の裏話を描いた「ライアーズ・ポーカー」で1989年にデビューしたマイケル・ルイス(Michael Lewis)が、2010年に発表した同名のノンフィクション。関係者へのインタビュー中心の構成で、これが映画になるのか?という著作ですが、さすがサタデー・ナイト・ライブ出身のアダム・マッケイ(Adam McKay)監督、起こったことのばかばかしさを逆手にとって、しっかり笑える映画に仕上げています。
サブプライムローンというのは、あまり信用のない人たちへの貸付のこと。なぜ信用のない人たちにお金を貸すのかといえば、住宅価格の高騰が続き、取得価格よりも高く売れる状態が続いたから。つまりローンを組んで家を買うと、その担保となっている家が値上がりしますので、仮に返済能力がなくても、最終的に家を売れば返済できてしまうわけです。原作には、ホーム・エクイティ・ローンを5軒分抱えたラスヴェガスのストリッパーのエピソードが登場しますが、当時は返済能力など無視し、どんどんローンを組ませて家を売りつけることが横行していました。
その結果、1990年代半ばに年間300億ドル程度だったサブプライムの貸し付け額が、2000年には1300億ドル、2005年には6250億ドルまで上昇したそうです。さらに、90年代半ばにはサブプライムローンの約65%が固定金利で組まれていたのに、2005年には75%が変動金利、それも最初の2〜3年だけ固定金利という“釣り金利”で組まれるようになります。2〜3年たつと金利が跳ね上がり、当然、払えなくなるのですが、担保の価値が上がっていますので借り換え可能。業者側にしてみれば、もう一度、ローンの手数料をせしめられてラッキー、借り手側からすれば、よくわからないけどそのまま住み続けられてラッキーというわけです。
もちろん、このウインウインの関係は住宅価格が上昇しているという前提が必須です。2006年に住宅価格が頭打ちになるとローンの滞納が増え始めます。住宅の価値が下がって借り換えできませんので差し押さえになり、それが売りに出されてさらに住宅の相場を引き下げます。そうして連鎖的に不良債権が増えていったのがサブプライムローン問題で、その結果、こういったローンを証券化したサブプライム・モーゲージを抱えていた金融機関が多額の損失を被り、ベアー・スターンズやリーマン・ブラザーズといった投資銀行が破綻することになります。
この映画の主人公たちは、サブプライムローンのいい加減さを見抜き、サブプライム・モーゲージのバブルがはじけることを予見した人たちです。映画の原題になっているショートとは空売りのことで、値下がりする側に賭ける取引ですが、彼らはサブプライム・モーゲージそのものを空売りしたわけではありません。サブプライム・モーゲージを束ねたMBS(Mortgage Backed Securities)を組み合わせて金融商品化したCDO(Collateralized Debt Obligation)に対するCDS(Credit Default Swap)を買いました。
このへんがわかりにくいところですが、CDSというのはスワップといいながら、スワップ取引ではなく保険です。つまりCDOが破綻したときに保険金を受け取る仕組み。
誰かの生命保険を支払うことに近い感じでしょうか。その人が早く死ねば、あまり保険料を支払わずに保険金を受け取れますので儲かりますが、なかなか死ななければ、保険料がどんどん嵩んでいってそのうち支払えなくなってしまいます。ですからこの物語の登場人物、サブプライムの破綻に賭けたブラウンフィールドキャピタル(実際はCornwall Capital)の二人組は、最後の局面で政府が救済してしまうのではないかと戦々恐々とします。債務不履行にならずそのまま生き延びてしまえば、保険料を払い続けなくてはいけないからです。
前置きが長くなりましたが、わたし自身、原作を読んだだけで、とくに債権に詳しいわけではありません。知人が @ms.com というアドレスからメールを送ってきたとき、マイクロソフトに転職したのだと勘違いしたほど投資銀行にも金融機関にも疎いのですが、この映画を観る前に、上に記した程度の理解があった方が気持ち良く楽しめると思います。
主な登場人物の一人は、クリスチャン・ベール(Christian Bale)演じるマイケル・バーリ(Michael Burry)。もともと医師でしたが、自分の取引を記した投資ブログが人気になり、サイオンキャピタル(Scion Capital)という投資ファンドを立ち上げます。少年時代に事故で片目を失っている上に、アスペルガー症候群で対人関係が苦手です。しかし、アスペルガー特有の細かい部分にこだわる性格で目論見書を隅々まで読破し、投資を成功に導いていきます。
スティーヴ・カレル (Steve Carell)演じるマーク・バウム(実際はSteve Eisman)は、フロントポイント(FrontPoint Partners)というファンドのマネージャーです。思ったことを口に出さずにいられない性格で、親会社のモルガンスタンレーから、優秀だけど一緒に仕事をしたくない人間だと思われています。少年時代、ユダヤ教の律法タルムードを熱心に読んでいると思ったら、タルムードの矛盾を探していたという変わり者。その妻を最近よくみかけるようになったマリサ・トメイ(Marisa Tomei)が演じています。
そして彼にCDSを売るジャレド・ベネット(実際はGreg Lippmann)はドイツ銀行ニューヨーク支店のサブプライム担当筆頭トレーダー。ドイツ銀行の本体がCDOを買いあさっている中、彼だけCDSの取引に目を付けます。演じているのはライアン・ゴズリング(Ryan Gosling)。
そして最後の変わり者は、ガレージバンドのような独立系ファンド、ブラウンフィールドキャピタルを運営している二人組み、チャーリー・ゲラー(実際はCharlie Ledley)とジェイミー・シプリー(実際はJamie Mai)。
そのメンターであるベン・リカート(実際はBen Hockett)はJPモルガンのシンガポール支店でトレーダーをしていた人で、金融業界に嫌気がさして足を洗ったという人物。彼を演じているのが、この映画のプロデューサーでもあるブラッド・ピット(Brad Pitt)で、そのせいもあって原作で描かれているよりずっと道徳的な人物になっています。
実際、原作でマイケル・ルイスが嘆いているのは、米国の金融業界は、ジャンクボンドで危機に陥り、LTCMのときも税金で救済したというのに、なぜまたサブプライムのバブルに突入してしまうのか、なぜ懲りないのか、ということです。そういう意味で、ブラッド・ピットのセリフの数々には、映画の冒頭で掲げられるマーク・トウェインの警句“It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so(問題は知らないことではない。知りもしないことを知っていると思い込むことだ)”と共に、この作品の本質的な部分が込められています。
マイケル・ルイスはソロモン・ブラザーズの債券セールスマンだったときの経験を暴露してデビューしたのですが、この映画の原作を当時のCEO、つまり上司だったジョン・グッドフレンド(John Gutfreund)に対するインタビューで締めくくってます。投資銀行の放逸ぶりは、合資銀行だったソロモン・ブラザーズを彼が株式会社に変えたとき、つまりリスクを自分たちから株主に移転させたときに始まったという話です。折しもつい先日、3月9日にジョン・グッドフレンド氏が亡くなりました。果たして彼はこの何度目かのバブル、彼が作りだした世界のなれの果てをどうみていたのでしょうか。
公式サイト
マネー・ショート(The Big Short)
[仕入れ担当]