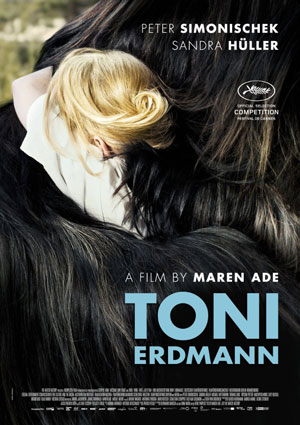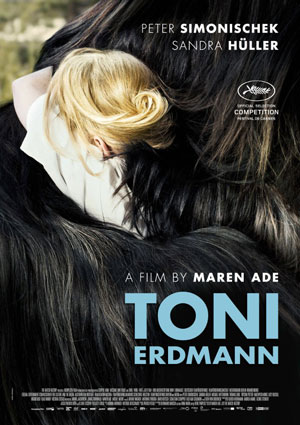 丁寧に作られた父娘のヒューマンドラマです。物語は、イタズラ好きの父親が、仕事一途の娘に人間らしい生き方をして欲しいとストーカー的にまとわりつくというもので、ただそれだけのお話なのに2時間40分強と長尺なのは、間の悪さがこの映画の持ち味だから。
丁寧に作られた父娘のヒューマンドラマです。物語は、イタズラ好きの父親が、仕事一途の娘に人間らしい生き方をして欲しいとストーカー的にまとわりつくというもので、ただそれだけのお話なのに2時間40分強と長尺なのは、間の悪さがこの映画の持ち味だから。
父娘の価値観のズレから生じる間の悪い感じが笑いを誘い、ちぐはぐだった気持ちが交差したとき感動に包まれます。
とても良い映画です。そして深い。一見、父親が主役のように見えますが、実は娘のイネスを描いた映画で、社会問題を巧みに取り込みながら、現代人が抱えるさまざまな矛盾や葛藤に光を当てていきます。働く女性なら何度も首肯する箇所があると思います。
映画の幕開けは、音楽教師である父親ヴィンフリートの自宅に荷物が届くシーン。配達業者の若者を相手に、一人二役のイタズラを仕掛け、若者を困惑させます。そして病身の老母を訪ね、生徒たちの演奏会に死に顔メイクで参加した後、そのメイクのまま離婚した妻の家に顔を出して、赴任先のブカレストから帰国していた娘イネスと再会します。
ちなみに、この演奏会で合唱したのはハネス・ヴァーダー(Hannes Wader)という人の曲で、ドイツでは左派系のシンガーソングライターとして知られている人だそうです。そのあたりがわかっているとヴィンフリートの立ち位置も見えてきそうですが、知らなくても面白さは変わりません。
さて、娘のイネスですが、戦略系コンサルで働いていて、ルーマニアで採油会社のリストラクチャリング・プロジェクトを担当しています。彼女の誕生日の前祝いで身内が集まったというのに、顧客企業へのプレゼンを控え、裏庭で電話にかかりきりです。一目で彼女の真面目な性格、ワーカホリックなライフスタイルが見て取れます。
電話を終えたイネスに、誕生日パーティをしているとは知らなかったので、来週、プレゼントを持ってブカレストに行こうと思っていたんだ、と言うと、いつでも好きなときに来て、と言われたヴィンフリート。帰り際、イネスに、祖母(彼の老母)の家で明日の朝食を取らないか、と誘いますが、10時のフライトで発つから無理だと断られます。エンディングの伏線となる会話です。
次に父娘が再会するのが、イネスの勤務先が入居するブカレストのオフィスビル。イネスが同僚と一緒にエントランスから入ってくると、ロビーでサングラスをかけたヴィンフリートが新聞を読んでいます。彼にしてみれば、サプライズを演出したつもりだったのでしょうが、イネスは気にせずセキュリティゲートを抜けていってしまいます。
とぼとぼオフィスビルから出てくると、すぐにイネスのアシスタントのアンカが追っかけてきて、ヴィンフリートに声をかけます。渡された電話でイネスと話して安心するヴィンフリート。
ここでちょっと面白いのはアンカとの会話です。彼女は現地採用のルーマニア人という設定ですので英語で話すのですが、他の場面でもビジネス会話は英語、父娘の私的な会話はドイツ語という使い分けになっていて、これがビジネスの浮薄なノリを強調する仕掛けになっています。
たとえばアンカとの会話で「うちの娘は上司としてどう?」と訊ねたヴィンフリートに、「彼女は私のパフォーマンスにたくさんのフィードバックを与えてくれます」とアンカが答え、思わず「パフォーマンスって仕事のこと?」と聞き返します。オフィスでは日常的な言葉であるfeedbackもperformanceも、ヴィンフリートにとって珍妙なジャーゴンでしかないのです。
これ以外にも、イネスの上司が「チームの結束が弱いので(team isn’t so tight)士気を高めたい(boost the team spirit)」と言ったり、後にトニ・エルドマンが「自分はコンサルタントでコーチングをしている」と自己紹介した際に「ご専門は?(What’s your focus?)」と訊ねられたり、いかにも、という表現がちりばめられていて、リアリティを高めながら、上滑りな言葉で支えられたビジネスの世界を皮肉っています。
普段からオフォスでこういう言葉を耳にしている非英語圏の人の笑いのツボを押す演出だと思います(英語でリメイクするときはどうするのでしょう)。
イネスと再会したヴィンフリートは、1ヶ月の休暇を取ってきた、と言って彼女を狼狽させますが、結局、すぐ帰国する予定だと彼女のアパートを後にします。もちろん、そこは一筋縄にはいかないヴィンフリート。妙なカツラと入れ歯で変装し、よれよれのスーツを来たトニ・エルドマンとして彼女の目の前に再登場します。
ブカレストでビジネスに明け暮れるイネスにつきまとい、彼女の価値観を変えさせようとする魂胆です。
最初は反発していたイネスも、次第にトニ・エルドマンの存在を受け入れていきます。その現れであり、この映画の見せ場の1つになっているのが、二人で訪問したルーマニア人の家庭でイネスが“Greatest Love of All”を熱唱するシーン。最初は笑いながら見ていた映画館の観客も、彼女がフルコーラス歌い上げる頃には共感の涙に暮れる名場面です。
もう一つの見せ場が、イネスの自宅で行う誕生日パーティ。これについては具体的に書きませんが、ポスターになっている毛むくじゃらの「クケリ」が登場し、これまた笑いが感動に変わっていく名場面だと思います。
冒頭で社会問題と書いたのは、先進国であるドイツから発展途上国であるルーマニアに赴任したイネスを通じて、経済格差を浮き彫りにしているところ。札びらで頬を張る、といったら言い過ぎでしょうが、エクスパットにありがちな傲慢さを身につけた娘を、普通の暮らしをしてきた父親が心配する構図になっています。また、イネスの友だちが、上海から来た中国人に不動産を売りつけたり時代性を感じさせる小ネタも盛り込まれています。
ドイツでは慎ましく暮らしているヴィンフリートですが、決して貧しいわけではありません。彼の自宅も、母親(イネスの祖母)の自宅も、元妻(イネスの母親)の自宅もきちんと設えられており、それなりの豊かさを感じさせますし、終盤で登場する親族もマラガで暮らしていると言っていますので(字幕ではスペインと表示されますが)、中流より上という設定だと思います。
そんな家庭できちんと育ったはずのイネスが、ビジネスの最前線に置かれ、発展途上国に赴任したことで、自分自身を見失ってしまいます。映画の中で語られる「義務に追われているうちに人生が終わってしまう」という言葉の裏には、まじめな女性だからこそ義務に追われてしまうという、男性中心のビジネス社会への批判も含まれていると思います。働く女性には是非ご覧になって欲しい作品です。
公式サイト
ありがとう、トニ・エルドマン(Toni Erdmann)
[仕入れ担当]