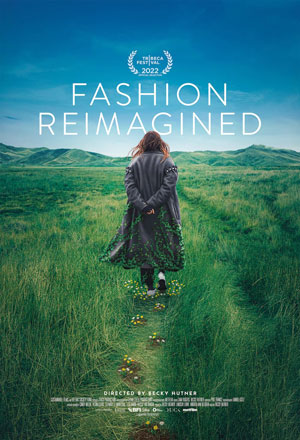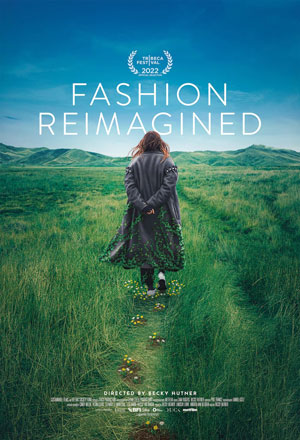 ファッションとサステナビリティ。この相容れそうにない二つを両立させようと奮闘するデザイナーを追ったドキュメンタリーです。主役はロンドンを拠点とする服飾ブランド“Mother of Pearl”のデザイナー、エイミー・パウニー(Amy Powney)と製品開発マネージャーのクロエ・マークス(Chloe Marks)ですが、おしゃれなファション映画ではありません。さまざまな難題を気合いで乗り越えていく“ド根性物語”です。
ファッションとサステナビリティ。この相容れそうにない二つを両立させようと奮闘するデザイナーを追ったドキュメンタリーです。主役はロンドンを拠点とする服飾ブランド“Mother of Pearl”のデザイナー、エイミー・パウニー(Amy Powney)と製品開発マネージャーのクロエ・マークス(Chloe Marks)ですが、おしゃれなファション映画ではありません。さまざまな難題を気合いで乗り越えていく“ド根性物語”です。
ファッション産業を国に例えると、その二酸化炭素排出量は中国、米国に次ぐ規模になるとエイミー・パウニーは言います。その典拠は不明ですが、たとえば2020年の国別排出量をみると、中国が約101億トン、米国が約43億トン、インドが約21億トンですから、日本の排出量(約10億トンで5位)を上回るレベルなのでしょう。ファストファッション興隆に伴う業界の拡大も要因の一つでしょうが、そもそも繊維業や縫製業は低開発国の主力産業ですから、環境配慮よりも生産量や価格競争力が優先されるのは仕方ありません。

ランカシャー出身のエイミー・パウニー。自然志向の両親のもとオフグリッド(off-grid)、つまり公共の電力などの供給を受けない自給自足の環境で育ちました。2002年にロンドンのキングストン大学(Kingston University)に進み、ファッションデザインを専攻します。中古のシェルスーツを着ていたという彼女の生育環境から考えると、やや突飛な印象もありますが、彼女いわく、トップショップやプライマークといったファストファッションが登場したことで、クラスの壁を打ち破ることができたとのこと。おそらくファッションが自由な世界への突破口のように感じられたのでしょう。
大学時代にナオミ・クライン(Naomi Klein)の「ブランドなんか、いらない(No Logo)」と出会います。躍進を続ける大手アパレルの影にはスウェットショップなどの問題が潜んでいることに気付くわけです。ここで社会活動家に転向していればありきたりな環境左翼になっていたのでしょうが、彼女の関心はキャサリン・ハムネット(Katharine Hamnett)に向かいます。ファッションを通じて社会変革を促していこうとするわけです。映画の中で“本当はセントラル・セント・マーチンズに進みたかったが2000ポンドの学費が捻出できなかった”と言っていましたが、その進路希望もキャサリン・ハムネットへの憧れ故だったのかも知れません。

2006年に大学を卒業し、キャサリン・ハムネットに応募しますが、採用されず、かろうじてマザー・オブ・パール(Mother of Pearl)に潜り込みます。マザー・オブ・パールは2002年にダミアン・ハーストの妻だったマイア・ノーマン(Maia Norman)が設立したブランドで、その人脈を活かした現代美術アーティストとのコラボレーションで人気を博していました。
カッティングルームのアシスタントとして採用されたエイミーは、ほどなくスタジオマネージャーに昇進し、2017年にはクリエイティブディレクターとしてロンドン・ファッションウィークに参加します。そこで英国ファッション協議会とVOGUEから英国最優秀新人デザイナーに選ばれ、一躍注目の人になるわけです。

そして2018年にサステナビリティに配慮したブランド、No Frillsを立ち上げることになるのですが、そこに至る道筋を記録したのがこの映画です。オーガニックまたは自然の素材を用い、環境負荷、人権、アニマル・ウェルフェアに関する社会的責任を果たすためのサプライチェーン透明化を謳うコレクションです。英国最優秀新人デザイナーの副賞である10万ポンドを使ってそれを達成しようというのです。
まずは素材選びということで、ミュールジング(Mulesing)せずに羊を育てている牧畜業者を探します。メリノ種の羊に対し、蛆虫の寄生防止策として糞尿が付着しやすい臀部の皮膚を切り取る処置で、一般的に麻酔をせず、傷跡の手当もしないことからアニマル・ウェルフェアの観点から問題視されているのですが、エイミーとクロエはそれを行わない牧畜業者に会うためウルグアイに飛びます。それがペドロ・オテギ(Pedro Otegui)で、彼との出会いがこのドキュメンタリーの軸となります。

環境負荷低減のために同じ地域で生産から加工まで手がけたいと、まずはウルグアイ国内を当たり、隣国ペルーでようやく受注してくれる紡績工場を見つけます。どこの工場も様々な生産者から集めた羊毛を加工しており、少ロットでシングルオリジンの注文には応じられないのです。トレーサビリティの確保がいかに困難か気付くわけですが、彼女たちはコットンについても同じこだわりで業者にあたります。

そこで行き着いたのがトルコの生産者。ただしここでも単一の農場で生産される綿花だけを使うことは難しく、GOTS認証の取得を条件にオーガニック素材としての信用を担保することになります。しかし発表3ヶ月前にペルーの業者から納期の問題でキャンセルされるというピンチに見舞われ、急遽、オーストリアの業者にウールの加工とジャガード織りを依頼することになるなど最後までギリギリの対応を強いられます。
そして入手可能になったウール50%+コットン50%の素材の他、木材由来のテンセルを加え、MOP初のサステナブル・コレクションが完成するのですが、その後もポルトガルなどで業者を探して理想を追い続けているそうです。キングストンの卒業制作のテーマがサステナビリティだったという彼女の執念が、ようやく実を結び始めるわけです。

そんな“ド根性物語”の映画を創り上げたのはトロント出身のベッキー・ハトナー(Becky Hutner)。これが長編映画デビュー作ですが、それまで17シーズンにわたってロンドン・ファッション・ウィークの映像を担当してきたそうで、その結果としてエイミーと出会い、彼女にとっても飛躍の一歩となりました。長期にわたってエイミーたちと旅をして、監督のみならずプロデューサーも務めた彼女の信念が結実した作品とも言えるでしょう。

公式サイト
ファッション・リイマジン(Fashion Reimagined)
[仕入れ担当]