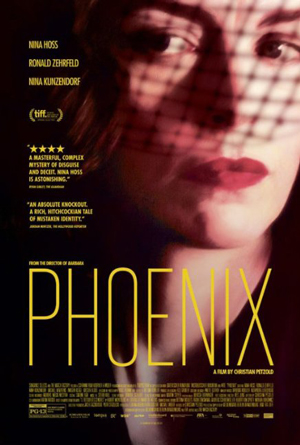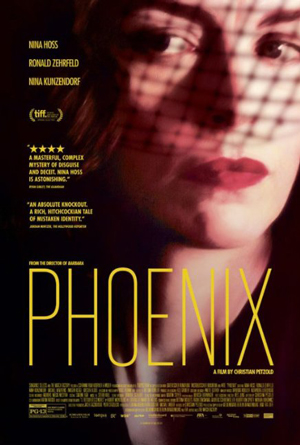 2012年のベルリン映画祭で銀熊賞(監督賞)を獲得した「東ベルリンから来た女」の監督、クリスティアン・ペッツォルト(Christian Petzold)が、同作で主役を務めたニーナ・ホス(Nina Hoss)とロナルト・ツェアフェルト(Ronald Zehrfeld)を再び起用して撮った作品です。
2012年のベルリン映画祭で銀熊賞(監督賞)を獲得した「東ベルリンから来た女」の監督、クリスティアン・ペッツォルト(Christian Petzold)が、同作で主役を務めたニーナ・ホス(Nina Hoss)とロナルト・ツェアフェルト(Ronald Zehrfeld)を再び起用して撮った作品です。
前作同様、ペッツォルト監督と、映画監督で批評家のハルーン・ファロッキ(Harun Farocki)が共同で脚本を書いていますが、前作と異なり、本作には原作があります。1963年にフランスのユベール・モンテイエ(Hubert Monteilhet)が書いた「帰らざる肉体」という小説で、1965年には“Return from the Ashes”という題で映画化されていますので、本作はリメイクになるようです。ちなみにファロッキ氏は2014年7月に急逝しています。
映画の舞台は終戦直後1945年のベルリン。ナチスの収容所還りの女性と、戦中まで彼女の夫だった男性が繰り広げる愛憎の物語です。前作に続いて、女性の自立という視点が大切なポイントになっているとはいうものの、粗っぽくまとめてしまうと、物語のベースは一種の心理サスペンスだと思います。
冒頭、検問の兵隊が、車の後部座席にいる顔中に包帯を巻いた女を訝しみ、車に乗り込んで確認しようとします。しかし、すぐさま「行って良い」と言い、彼女の顔がいかに無残な状態かを観客に説明するわけですが、この短いシーンで時代背景から同時代を生きる人々の心情まで、さまざまな事柄を一気に説明してしまう上手い幕開けです。
包帯の女性はニーナ・ホス演じるネリー。強制収容所からの生還者です。彼女を連れ帰ってきたレネは、顔の再生手術を受けさせた後、パレスチナへ渡ってユダヤ人国家を樹立しようと考えているシオニストですが、拘束時に離ればなれになった夫ジョニーとの再会のことばかり考えているネリーはレネの話に耳を傾けません。
その後、再生手術の傷も癒え、ネリーは夜の街でジョニーを探し始めます。なぜ夜の街かといえば、二人は元々ミュージシャンで、ジョニーはピアニスト、ネリーはシンガーとして働いていたからです。そして、本作の原題でもある“Phoenix”という米兵相手のクラブで下働きをしているジョニーを見つけます。
ロナルト・ツェアフェルト演じるジョニーは、顔が変わってしまったネリーが誰だかわかりません。それどころか、あなたは収容所で死んだ妻に似ているので、妻のフリをしてくれれば、死に絶えた妻の一族の財産を横取りできると提案します。つまりネリーは、自分自身のニセモノを演じて欲しいと頼まれるわけです。
そこでジョニーのことを諦めてしまえば話は終わりですが、ネリーは、夫の真意を確かめたくて、エスターという偽名を名乗って、ネリーになりきる練習を始めます。
もちろん、ネリーには、そのうち自分が誰だか気付くだろうという淡い期待があるのですが、ジョニーは妻が死んだものと頑なに信じ込んでいます。その理由はネリーが収容所送りになる経緯と関係していて、それが次第に明かされることでネリーも変化していくという物語です。
そこで重要な小道具となるのが音楽。クルト・ワイル(Kurt Weill)の“Speak Low”と“Berlin im Licht”、コール・ポーター(Cole Porter)の“Night and Day”が印象的に使われています。中でも“Speak Low”は本作の主題曲というべき位置づけの音楽で、映画の終盤、ネリーがこの曲を歌うシーンには心打たれるものがあります。
それから個人的に響いたのは、レネのその後。
映画「イーダ」も似た展開でしたが、戦争の瑕というのは、気丈に振る舞っていても心の奥底に深く刻まれているものだということを示したのでしょう。小さな場面ですが非常に重い、ペッツォルト監督らしい表現だと思いました。
公式サイト
あの日のように抱きしめて(Phoenix)
[仕入れ担当]